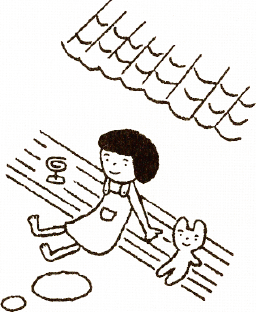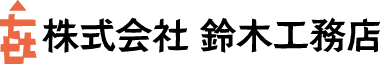季刊誌『かきのたね』で連載している「徒然とおる」から。vol.58 徒然とおるのまち歩きをおたのしみください。

清洲橋
関東大震災後、東京の都市再生は、単なる復旧にとどまらず、新たな美と機能を備えた「帝都」の創造へと向かっていました。その象徴のひとつが、隅田川に架けられた9つの「復興橋」です(後に相生橋は架替)。震災で多くの橋が崩壊・焼失し、耐火性・耐震性が求められました。同時に当時の内務省復興局は、都市景観を彩る「美しい橋」をめざし、設計と構造に新たな思想も注ぎ込みました。

永代橋
永代橋1926年(大正15年)、蔵前橋27年、言問橋28年、そして清洲橋28年。これら復興橋は、機能性と美しさを兼ね備えた橋梁として、一つひとつに異なる個性が宿ります。たとえば永代橋(国の重文)は、重厚なアーチ構造と直線的な力強さが印象的な鋼製3連タイトアーチ橋。威厳を感じさせる姿で都市の復興を支えました。

蔵前橋
一方、蔵前橋は鮮やかな黄色に塗装され、隅田川沿いの街並みに彩りを添えています。当時としては珍しい色彩計画が導入され、都市と調和する景観設計の先駆けとなりました。そして、静かな存在感を放つのが言問橋。鉄筋コンクリートアーチ橋でありながら、控えめな美しさの中にアールデコ装飾を潜ませ、対岸の風景をやさしく引き立てます。

言問橋
個性派ぞろいの復興橋の中で最も人々の記憶に残る橋といえば、やはり清洲橋(国の重文)。ケルン吊橋がモデルと言われ、水面に浮かぶような優雅なチェーン吊橋です。青く塗られたケーブルと主塔の繊細な曲線は、どこかヨーロッパの都市に迷い込んだかのような幻想を抱かせます。橋もまた、まちの記憶と景色を編む、大切な「建築」なのだと改めて思います。

清洲橋
ファーストが求められた震災の瓦礫の中から生まれた復興橋ですが、ただの交通手段ではない、時代の精神と技術者たちの美意識が結集した「橋橋」です。
(鈴木)